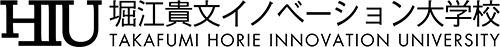堀江貴文イノベーション大学校(以下、HIU)では、5名のメンバーを対象にしたベーシックインカム実験が開始されました。HIUは毎月10万円を支給し、メンバーはこの資金を自身の活動に自由に活用できます。資金の使い道は完全にメンバーの裁量に委ねられています。この実験の進行状況は、毎月のレポートでお伝えしていきます!
教科書の“前方後円墳”が、お墓になる日。

久しぶりにHIUの定例会に行ってきました。今月のHIU定例会のゲストは宮迫博之さんと竹田恒泰さんです。
特に印象に残ったのは、竹田恒泰さんが古墳型のお墓をつくり、販売していくという事業を展開していることでした。
その名も「株式会社前方後円墳」! このネーミング、最高ですね(笑)。
社会科の教科書で見た、あの「前方後円墳」型のお墓に亡くなった方の御骨を納めるという、とても面白い事業です。
「歴史ロマンと現代のビジネスを融合させる」という発想が本当に斬新でした。
――――――――――
株式会社前方後円墳
https://kofun.co.jp/
――――――――――
実は僕も子どもの頃、社会科の授業を受けているときに「古墳みたいなお墓があってもいいのに」と思ったことがあります。 「自分が死んだら前方後円墳に入りたい」なんて想像、誰もが一度は考えたことがあるのではないでしょうか。 それを実現してしまう竹田さん、さすがです。
もちろん、事業の課題もあります。古墳といっても結局は「お墓をつくること」になるので、自治体との協力が必要不可欠です。 お墓は法律や条例で厳しく規制されているため、「古墳型のお墓を建ててもよい」と理解のある霊園を探しているようです。これは簡単なことではないでしょうね。
それでも、僕はこの事業に大きな可能性を感じています。というのも、僕自身、自然豊かな山の中の霊園で、祖母がつくったおいしいおにぎりを食べるのが、お墓参りでのいちばんの楽しみでした。 祖父が車を運転して一時間かけて山の中の霊園へ向かい、着くとお墓参りをして、楽しみのお昼ごはん。緑の中で食べるおにぎりは格別でした。
お墓参りは、本来は悲しい場所ではなく、「大切な人を偲びながら、自分も人生を見つめ直す場所」であってほしいと思います。 だからこそ、お墓参りを最高の思い出にできる場所づくりをしてほしい。前方後円墳という歴史ロマンあふれる形なら、家族でピクニックがてらお墓参りに行く――そんな文化が生まれるかもしれません。 「死」をタブー視するのではなく、むしろ前向きに向き合える場所づくり。これは本当に意義深いプロジェクトだと思います。
――――――――――
古墳の窓口
https://madoguchi.kofun.co.jp/
――――――――――
自分の声をAIに DラボAIで学んだElevenLabs

最新のAI技術を教えてくれる「DラボAIチャンネル」で、今月もいろいろと学びました。AIの進化は本当に速いので、常に最新情報をキャッチアップしていく必要があります。 その中でも特に興味深かったのが、「自分の声をAIにする」ツールでした。 以前から、堀江貴文さんの声を真似たAIがTwitterなどでよく話題になっていて、「これは面白そうだな」と興味は持っていました。でも、なかなか手が出せずにいました。 「難しそう」「どこから始めればいいかわからない」という心理的ハードルがありました。 でも今回、DラボAIチャンネルで配信されているのを見て、「これなら僕にもできるかも!」と思い、実際にサイトに登録してみました。 使用したAIの名前は「ElevenLabs」。音声合成AIとしては非常に高品質なサービスです。
実際に自分の声を収録するには何が必要なのか、まずは公式ガイドをしっかり読むことから始めました。「基本を押さえることが成功への近道」です。
声の収録で特に気をつけたことは、「普段どおりの声で一発撮りをすること」でした。
ElevenLabsのようなボイスクローン技術は、単に声のトーンやピッチを模倣するだけでなく、それぞれの声の違いを生む微妙な特徴や抑揚まで捉えることができます。AIの精度は驚くほどのレベルに達しています。
特に驚いたのは、言葉と言葉の間隔まで正確に測っているということでした。ボイスクローンが登場した当初は「間が空かないように編集して提出する」という作業が必要でしたが、今ではそれすら不要になっています。
では、安定したトーンやピッチで話せて、言葉と言葉の間隔もぶれない撮り方は何か? と考えた結果、「一発撮りしかない」という結論に至りました。
編集でつなぎ合わせると、どうしても微妙なトーンの変化や間の不自然さが生まれてしまいます。自然な話し方をそのまま収録するのが最善の方法でした。
ただし、ElevenLabsもバージョンアップを続けているため、声をアップグレードするか、再度収録し直す必要が出てきています。AIの進化に合わせて、僕たちも常にアップデートしていく必要がありますね。
速いだけのAIに戻れない。ChatGPT 5 Pro体験

検索の代わりに情報を調べたり、メッセージの添削や記事の執筆、アイデア出しの壁打ち相手として使ったりと、今やAIは多くの場面で活用されています。
僕自身も、気がつけば日常のさまざまな場面でAIを使うことが増えてきました。もはや「AIなしでは仕事にならない」というレベルかもしれません(笑)。
そこで今回導入を決めたのが「ChatGPT 5 Pro」です。
正直、最初は値段を見て「うわ、高い……」と手が出ませんでした。月額課金のサービスですから、躊躇する気持ちもわかりますよね。
でも、調べていくうちにさまざまな利点が見えてきました。特に重要だったのは、ハルシネーション(AIが事実と異なる情報を提示する現象)の大幅な低下や、IQレベルの向上による推論能力の改善です。これらのメリットを考えると、「試してみる価値はある」と判断しました。
AIが間違った情報を出してくることのリスクを考えれば、精度の高いツールに投資する意味は十分にあります。「安物買いの銭失い」にならないよう、まずは試してみることにしました。
ChatGPT 5 Proに課金してみて、特に印象が強かったのは、調べものの質が一段と上がったということでした。
よく「研究者や専門職に従事している人にしかChatGPT 5 Proへの課金は適さない」と言われますが、これは日本語の「研究」という言葉のニュアンスとは少し違いました。
ChatGPT 5 Proは、単なる情報検索を超えて、「調べる」という行為そのものを深く支援してくれます。まさに「知的パートナー」といった感じです。
確かに処理には時間がかかります。仕事で使っていると、まるでタバコ休憩に行ってしまう人が出るほどの長さです(笑)。「ちょっと一服してくるか」みたいな。
でも、その待ち時間を上回るほどの価値があります。
新しい情報はもちろん、自分では考えつかなかった新しい視点や道筋を提案してくれます。これは本当に面白いAIです。
「時間がかかる=質が高い」という、ある意味当たり前だけど忘れがちな真理を思い出させてくれます。速さだけを求めるなら無料版で十分ですが、深い洞察がほしいならProに投資する価値は十分にあるということです。
最近は、他言語のメールの翻訳や書き換え、記事の執筆などをAIに任せています。
まだ文体は硬く、日本語の執筆には適していない部分もありますが、「やさしい文章にして」などと指示すると、きちんと柔らかい表現に変えてくれます。プロンプト次第で改善できるのが面白いですね。
特に興味深いのは、日本語と他の言語では、書き方が自然と変わることです。
「その言語の話者に伝わるように書いて」と指示すると、単なる直訳ではなく、その文化圏に合った書き方に変えてくれます。これは従来の翻訳ツールにはなかった、まったく新しい使い方です。
「言語は単なる言葉の変換ではなく、文化的コンテクストの変換でもある」ということを、AIが理解し始めているのだと感じます。
さらに、面白い使い方をしている友人もいました。「ペットの健康検査の結果をGPTに投げている」というのです。これは目から鱗でした。
それを聞いて、僕も次の実験として自分自身の健康診断の結果を画像などで送付して、新しい病気の予防の補助的な立ち位置でも使ってみようかと思っています。これは予防医療にも役立ちます。
もちろん、AIの診断を医療の代わりにするわけではありません。でも「セカンドオピニオン的な視点」や「見落としがちなリスク要因の指摘」など、補助的な役割は十分に果たせるはずです。
AIの活用範囲は、僕たちの想像を超えて広がっています。
p.s. ちなみに、この文章はChatGPT 5 Proで校閲しています。
ベーシックインカム生活の内訳:今月のお金の行き先はこちら

≪サービス≫
・DMMオンラインサロン「堀江貴文イノベーション大学校(通称:HIU)
https://lounge.dmm.com/detail/87/index/
・ブロマガ「堀江貴文のブログでは言えない話」
https://zeroichi.media/with/1242
・各分野で活躍するプロフェッショナル同士の雑談を楽しむことができる「ZATSUDAN」
https://zatsudan.com/
・クラシック音楽専門音楽配信サービス「ナクソス・ミュージック・ライブラリー」
https://ml.naxos.jp/
・『人生を変える 知識が詰まったNetflix』を目指してつくった「D-Lab by メンタリストDaiGo」
https://daigovideolab.jp/
・ワイン初心者も大丈夫。この世に まだ隠れているおいしさやワインの魅力をお伝えする「D-Labワインチャンネル」
https://daigovideolab.jp/wine/landing
・美味しすぎる健康的な料理方法を教えてくれる「つっしーの料理チャンネル by D-Lab」
https://daigovideolab.jp/cooking/landing
・このチャンネルは、より詳細な情報を教えてくれます。「かなりパレオな男チャンネルby D-Lab」
https://daigovideolab.jp/paleo/landing
・「Dラボ」に関する知識をすべて持ったAIと会話でき、最新のAIの技術を教えてくれる「D-Lab AIチャンネル」+「AI拡張プラン」
https://daigovideolab.jp/ai/landing
・保護猫と一緒に人生を切り拓く「D-Lab WiFi」「D-Lab SIM」
https://xmobile.ne.jp/d-labwifi/
・自分の人生を保護猫とともに変えていくお部屋「D-Lab CAFE」飲食代
(※入場には「D-Lab WiFi」「D-Lab SIM」契約者とその同伴者のみ)
https://dlabcafe.com/
・グラフィックデザインや動画編集、ウェブデザインの可能性を広げる「Adobe Creative Cloud」
https://creativecloud.adobe.com/ja
・電気もガスも、カブアンドで未来を先取り!「KABU&」
https://kabuand.com/
・仕事を減らす AI ではなく、あなたの “知りたい” を、一瞬で。「ChatGPT 5 Pro」
https://openai.com/ja-JP/chatgpt/overview/
≪飲食物≫
・カロリーゼロでコーヒーに砂糖を入れれます。「NuNaturals, Concentrated Simple Syrup, 16 fl oz (0.47 L)」
https://iherb.co/i1aX3WY
・他Dラボにて学んだ食事や料理方法を実践中
レポート執筆者:床次 佳浩 / Yoshihiro Tokonami
編集:D-Lab AIチャンネル「D-Lab AI」
https://daigovideolab.jp/ai/landing
校閲:OpenAI「ChatGPT 5 Pro」
https://openai.com/ja-JP/chatgpt/overview/
画像(一部):Adobe Firefly
https://firefly.adobe.com/
最新記事 by 床次 佳浩 / Yoshihiro Tokonami (全て見る)
- 『ベーシックインカムがくれた「自分を知る余白」』HIUベーシックインカムレポート【1月】 - 2026年1月31日
- 『20人の共犯者と始める、AI公開実験とプレゼン革命』HIUベーシックインカムレポート【12月】 - 2026年1月1日
- 『ベーシックインカム実験とAIが教えてくれた「価値のつくり方」』HIUベーシックインカムレポート【11月】 - 2025年11月30日