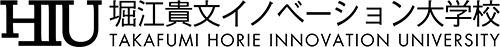堀江貴文イノベーション大学校(以下、HIU)で5名のメンバーを対象にベーシックインカム実験がスタートした。毎月HIUより10万円が支給され、メンバーはその資金を自身のアクティブな活動の為に使っていく。どう使うかはメンバー次第。果たしてどうなっていくのか!? 毎月レポートを掲載!
片手の音楽、画面の向こうへ
![]()
4月19日の夜、YouTubeで配信した私のピアノ演奏は、予想をはるかに上回る反響をいただきました。
今回の配信は、私が片手のみで演奏する少し変わったスタイルのコンサートです。外出自粛が続くなか、音楽で日常からひととき解放されてほしい――その思いで企画しました。クラシック音楽は堅い印象を持たれがちですが、実は人間のあらゆる感情を映し出す豊かなエンターテインメントです。
ふたを開けてみると、普段の対面の演奏会では到底埋まらないほど多くの方が集まってくださいました。移動を伴わないオンライン配信だからこそ、これまで会場にお越しになれなかった遠方の方々にも気軽に参加いただけたのだと思います。画面の向こうにこれだけの方がいらっしゃるのかと実感し、心地よい武者震いすら覚えました。
ステージは、私の自宅。いつも練習しているピアノから、極めてプライベートな空間のまま音をお届けしました。
選曲は、クラシックの面白さを凝縮したラインナップです。誰もが一度は耳にしたことのあるバッハの有名な前奏曲で幕を開け、《エリーゼのために》でやさしく誘い、続いて私の真骨頂であるスクリャービンの《左手のための小品》で「片手でこんな響きが?」という驚きを味わっていただく。そして、もはや私の代名詞になりつつあるゴドフスキー編《別れの曲》へ。
アンコールでは、いまの状況だからこそ届けたい思いを込めて、《花は咲く》を演奏しました。どんな困難のなかでも希望は芽吹く――その信念を音に託しました。
……と、ここまでは気持ちよく演奏し無事に配信を終えたのですが、ひとつ致命的な課題がありました。音質です。使用した一般的なウェブ用マイクは、人の声のような単純な音は得意でも、ピアノ特有の複雑な倍音や豊かな響きの再現は難しく、結果として音割れやこもりが生じました。ご視聴くださった皆さまには心よりお詫び申し上げます。準備不足を痛感しつつ、今回の反省を次に確実につなげます。
そこで、次回の5月6日の配信では音響機材をプロ仕様に一新し、ピアノのニュアンスを余さずお届けできる環境を整えます。クラシック愛好家の皆さまにもご満足いただける音での再挑戦となりますので、どうぞご期待ください。
たった1週間で配信へ。配信コンサートの舞台裏
![]()
先日の配信ピアノコンサートは、企画から開催までわずか1週間で実現しました。常識的には無謀なスケジュールですが、いくつかの幸運と、私自身の決断がかみ合った結果だと感じています。
きっかけは、私が所属するオンラインサロンHIUでの友人の一言でした。「HIU万博というオンライン文化祭をやるけれど、誰か参加しない?」――チャンスは、たいていこうした何気ない形で訪れます。多くの人が「準備が整っていないから」と見送る場面でも、私は前に進むことを選びました。
というのも、政府の「緊急事態宣言」以降、私はずっと考えていたのです。家に閉じこもらざるを得ない人たちのために、インターネットを使って何かできないか。ピアノの演奏を届けられないか、と。そうした思いが胸の内に積み重なっていたところへ、友人の募集が重なりました。もはや、やらない理由はありませんでした。
もちろん、思いだけでは前に進めません。行動に移してこそ、アイデアは価値を持ちます。幸運だったのは、その直前にHIUに「放送学部」という新しい部門が立ち上がり、私はそこでライブ配信の具体的なノウハウ――たとえば配信ソフト「OBS」の扱い――を学んでいたことです。
必要なのはスキルだけではなく、道具も同じです。映像をPCに取り込むための小さな機器「キャプチャーボード」が不可欠でしたが、当時は配信需要の急増で市場からほとんど姿を消していました。入手は困難、どこも品切れ。私は配信の2日前、最後の望みをかけて秋葉原へ向かい、電気街を何軒も回りました。そして、ある店の片隅で、ほこりをかぶっていた「最後の一台」を見つけたのです。あのときの高揚感は今も忘れられません。まるでRPGで伝説の武器を手に入れたような気持ちでした。
迎えた当日。映像はプロ用ハンディカム、声はワイヤレスヘッドセットでクリアに――完璧な布陣のはずでした。ところが直前の最終チェックで、信じがたいトラブルが判明します。ハンディカムから送られてくるピアノの音が、なぜか半音ほどズレて聞こえるのです。自分の指が出す音と耳から入る音が一致しないのは致命的で、このままでは演奏に集中できません。
時間は刻一刻と迫ります。ここで中止を選ぶのは得策ではありません。私は即座にプランBへ切り替え、映像はハンディカムを生かしつつ、ピアノの音はPCの内蔵マイクで拾うことにしました。結果として音質は十分とは言えませんでしたが、配信を止めるよりははるかに良い判断だったと考えています。
振り返れば、発案から画像制作、機材調達、配信までを1週間でやり切った自分に、私自身がいちばん驚いています。よく「運も実力のうち」と言われますが、実際には、準備と行動があってこそ運は味方をしてくれるのだと思います。
「インターネットでピアノコンサートをしたい」と思いながらも、私は長く「準備が完璧ではない」「もっと良い機材が必要だ」と先延ばしにしていました。けれど、友人の一言に背中を押され、見切り発車で走り出してみると、意外にも道は開けました。結局のところ、人はやってみることでしか自分の限界を知ることはできない。そして多くのことは、やってみると「思っていたより難しくなかった」と感じられる。もちろん、そのためにはトラブルを乗り越える覚悟と、「まずは80点で仕上げる」という割り切りも必要です。行動した者だけが味わえる達成感こそ、最大の報酬だと実感しました。
高音質配信への再挑戦

今月も、HIUなどDMMオンラインサロン入会継続¥11,000-をはじめ、ホリエモンチャンネル¥880-、クラシック音楽専門音楽配信サービス「ナクソス・ミュージック・ライブラリー」¥2,035-、ニコニコ動画「メンタリストDaiGoの「心理分析してみた!」」¥550-、あらゆる領域の映像制作を後押しするオンライン・コミュニティ「UMU TOKYO」¥2,700-、グラフィックデザイン及び動画編集、ウェブデザインのアプリケーションソフトウェアを利用できる「Adobe Creative Cloud」¥5,478-に使用する。
前回のピアノ配信で、私は最大の課題である音質に敗れました。せっかく集まってくださった皆さまに最良の音を届けられなかった――この借りは必ず返さなければなりません。そこで私は、クラウドファンディングに踏み切りました。
CAMPFIREで「5月6日の次回配信で、プロ水準の高音質をお届けする」というプロジェクトを立ち上げました。これは私の再挑戦であり、皆さまへの約束です。
とはいえ、この計画は私が気持ちよくなるためだけのものではありません。「最高の配信」にこだわるのには、より切実な理由があります。
それは、コロナ禍で苦境に立つ大切な人たちのためです。お世話になった大学の先生や、共に音楽を志した友人たち――彼らの営む店や教室が、いままさに存続の危機に瀕しています。私にできることは何か。片手しか使えない私でも、インターネットという武器を使えば、力になれるのではないか。
具体的には、私が整える高品位な配信環境を生かして、彼らの活動を紹介したり、チャリティー配信を企画したりすることができます。音楽を「支援の入口」へとつなぐためには、視聴者の心を動かすだけの品質が不可欠です。
そこで皆さまにお願いしたいのが、機材購入へのご支援です。目標金額は35万円。これで、ピアノの繊細な響きを的確に収録できるレコーダー/オーディオインターフェース(ZOOM H6)と、複数カメラの映像を番組のように切り替えられるスイッチャー(Roland VR-4HD)を導入します。
本プロジェクトは、目標金額に1円でも満たなければ全額返金となる**「All-or-Nothing」方式**です。皆さまのご協力がなければ、再挑戦も、仲間を支える計画も、すべてが水泡に帰します。まさにハイリスク・ハイリターンといえる仕組みです。
これは単なる寄付のお願いではありません。最高の音楽配信という作品を共に創り、その力で困っている人を支える――そのプロジェクトへの参加チケットだと考えています。どうか、私の再挑戦のパートナーになってください。
なお、クラウドファンディングのページは、慣れないPhotoshopと格闘しながら自作しました。プロのデザイナーに依頼する余裕はありませんでしたが、「使えるものは何でも使う」の精神で、素材は工夫して整えました。見た目は未熟でも、このページには私のささやかなスキルと、ありったけの思いを込めています。
そして、この無謀な挑戦のタイムリミットが刻一刻と迫っています。**締切は5月5日(火)23時59分。**この時間を1秒でも過ぎれば、物語はバッドエンドで強制終了です。
「All-or-Nothing」は残酷なまでに正直です。35万円に1円でも届かなければ、皆さまからの温かなご支援はすべてキャンセルされ、私の手元には何も残りません。つまり、「自分一人くらい参加しなくても大丈夫だろう」という一人ひとりの判断が、結果を左右し得るのです。
さて、あなたはどうしますか。 傍観者として結果だけを見届けるのか。 それとも当事者として、私とともに「最高の音楽で仲間を支える」未来を、その手でつかみ取るのか。
あなたのひと押しが、私たちの未来を変えます。プロジェクトページでお待ちしています。
レポート執筆者:床次 佳浩 / Yoshihiro Tokonami
https://x.com/MrTokosmusiclab
編集:D-Lab AIチャンネル「D-Lab AI」
https://daigovideolab.jp/ai/landing
校閲:OpenAI「ChatGPT Pro」
https://openai.com/ja-JP/chatgpt/overview/
最新記事 by 床次 佳浩 / Yoshihiro Tokonami (全て見る)
- 『20人の共犯者と始める、AI公開実験とプレゼン革命』HIUベーシックインカムレポート【12月】 - 2026年1月1日
- 『ベーシックインカム実験とAIが教えてくれた「価値のつくり方」』HIUベーシックインカムレポート【11月】 - 2025年11月30日
- 『約300作の中、準グランプリを取りました!』HIUベーシックインカムレポート【10月】 - 2025年10月31日