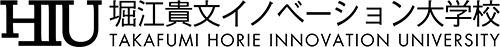堀江貴文イノベーション大学校(以下、HIU)では、5名のメンバーを対象にしたベーシックインカム実験が開始されました。HIUは毎月10万円を支給し、メンバーはこの資金を自身の活動に自由に活用できます。資金の使い道は完全にメンバーの裁量に委ねられています。この実験の進行状況は、毎月のレポートでお伝えしていきます!
ひとり動画制作で見えた時間の真実

来年にやろうと思っていた動画制作を、思い切って前倒しで始めました。約8年ぶりに、YouTubeへ動画を3本アップロード。8年のブランクは、やっぱり長いものですね。
来年は「どうすれば長くピアノを弾き続けられるのか」を一つのテーマに、少しずつ掘り下げていく予定です。私にとっては、才能以上に継続が何より大切だと感じています。
実は、ずっと動画を上げたい気持ちはありました。ただ、カメラワークや編集、デザインがよく分からず、気づけば約8年も手を付けないままに……。いわゆる「完璧主義に足を取られる」状態だったのだと思います。それでも今回は、「完璧じゃなくていい。まず始めよう」と決められました。まず一歩を踏み出せたこと自体が、いちばんの成果かもしれません。
8年前にも動画を2本ほど投稿しましたが、そのときは母校・大阪芸術大学のサークル「放送研究会」に加え、NHKの方にも関わっていただくなど、とても恵まれた環境でした。やはりプロのサポートがあるのとないのとでは大違いです。
今回は、撮影から編集まで完全にひとりで挑戦しました。HIUをはじめ、映像制作のオンラインコミュニティで学んだノウハウやデザインのアイデアが、ようやく自分の中で形になってきて、「学んだことを実践に移す」タイミングが来たのだと感じています。編集ソフトの操作は検索ですぐ調べられる時代ですが、実際に通しでやってみて強く感じたのは、想像以上に時間がかかるということでした。
たとえば、撮影自体は10〜30分で終わっても、その後の編集に2〜3時間。さらに、YouTubeのトップに並ぶサムネイルづくりにも1〜2時間かかることに気づきました。どんなに内容がよくても、サムネイルで興味を引けなければ見てもらえません。つまり、30分の撮影に対して、編集とサムネイルで合計3〜5時間――撮影時間の6〜10倍の時間が編集に流れていく計算です。これは、やってみて初めて分かったことでした。
そこで、時間短縮に向けて効率化も進めています。たとえばエンディングロールは事前に作り込み、繰り返し使える部分はテンプレート化する、といった工夫です。
ちなみにエンディングでは、Webで人気のドラマ『港区おじさん』の一部をアレンジし、ゴドフスキー作曲『ショパンのエチュードによる53の練習曲集』第5番(Op.10-3、いわゆる「別れの曲」)を演奏しています。ゴドフスキー版はショパンの原曲をさらに発展させた超絶技巧の編曲。エンディングにも自分なりのこだわりを込めました。
エンディング曲は2019年12月19日、ピアノカフェ・ベヒシュタインで録音しました。ドイツの名門らしい、柔らかく深みのある音色に助けられ、贅沢な環境での収録となりました。いっぽう、今回の動画3本は2019年12月5日、国際障害者交流センター「ビッグ・アイ」で撮影。すべてを一度にではなく、目的に合った環境を選ぶことで、時間はかかっても結果的に質の高いコンテンツに近づけた気がします。
8年ぶりの動画投稿。しかも、撮影から編集までをひとりでやり切れたことは、私にとって大きな一歩でした。ここから、少しずつ続けていきます。
客席が消えるホールと銀座の拍手

街角に「だれでも弾けるピアノ」が増えてきました。ストリートピアノの文化は、日本でもすっかり根づきつつあります。 今月もいくつかのストリートピアノを弾きに出かけ、演奏依頼も4〜5件ほど増えました。少しずつ活動の輪が広がっているのを感じて、うれしい限りです。
最初に訪れたのは、東京・銀座の百貨店「銀座三越」。高級百貨店にストリートピアノという組み合わせは、新鮮で面白いですね。 賑わっているだろうと思って現地に行くと、当日は人通りが少なく、ピアノがぽつんと置かれているだけ。「あれ、想像と違うな」と感じました。 それでもピアノの前に座って弾き始めると、終わった瞬間にたくさんの拍手をいただきました。この体験は今でも心に残っています。 「音楽は、聴かれて初めて価値が伝わる」——見ているだけでは伝わらなくても、音が鳴った途端に心が動く。あらためて音楽の力を実感しました。
高校時代からお世話になっている劇場から演奏依頼をいただき、関西へ。会場は大阪・堺市の国際障害者交流センター「ビッグ・アイ」です。 ふだんは客席が広がるホールですが、この日はまったく別の光景。客席がすっかり姿を消し、立食ができるスペースへと変わっていました。「同じ会場?」と思うほどの変化です。 ビッグ・アイには客席やフロアを上下できる舞台機構があり、客席を地下に収納したり、フロアをステージと同じ高さにそろえることができます。日本の劇場技術の高さを感じました。
その仕組みのおかげで、当日は食事を楽しみながら演奏を聴けるという、従来のクラシックとは少し違うカジュアルな空間ができ上がりました。 以前から「グルメありの演奏会を開いてみたい」と思っていたので胸が高鳴りましたが、いざ本番のころには皆さんまだお食事前。ちょっと肩すかしでしたが、次回こそ実現したいです。
翌朝は、同じホールで YouTube の動画撮影も行いました。大学時代のようにテイクを50回も重ねることはなく、撮り直しがぐっと減ったのがうれしかったです。 完璧を求めすぎず「良い演奏」を目指せるようになり、一度で納得できるテイクが増えました。技術面の向上はもちろん、心の持ち方が少し大人になったのだと感じています。
たまたまベヒシュタイン(世界三大ピアノの一つ。ほかはスタインウェイとベーゼンドルファー)の方とご縁があり、翌日はベヒシュタインが運営する「ピアノカフェ・ベヒシュタイン」へ。 店内にはピアノとチェンバロが置かれ、注文すれば自由に弾ける仕組みです。「コーヒー一杯でベヒシュタインが弾ける」——ピアノ好きにはたまらない空間ですね。 両方の楽器を試弾したあと、YouTube 用の撮影も行いました。ここがエンディング曲の収録場所にもなりました。落ち着いた店内の雰囲気とピアノの音色がよく溶け合い、音楽を聴く・演奏する環境として理想的だと感じました。
関西での演奏、ビッグ・アイでの撮影、そしてベヒシュタインカフェでの収録。どれも充実した時間でした。音楽を通じた出会いが次の機会へつながっていく——その流れを、これからも大切にしていきます。
スクルージ紙幣まで。堀江貴文氏ミュージカルの“作り込み”

今月も、HIUなど、DMMオンラインサロン入会継続¥10,800-をはじめ、ホリエモンチャンネル¥864-、クラシック音楽専門音楽配信サービス「ナクソス・ミュージック・ライブラリー」¥1,998-、ニコニコ動画「メンタリストDaiGoの「心理分析してみた!」」¥540-、あらゆる領域の映像制作を後押しするオンライン・コミュニティ「UMU TOKYO」¥2,700-、グラフィックデザイン及び動画編集、ウェブデザインのアプリケーションソフトウェアを利用できる「Adobe Creative Cloud」¥5,478-に使用する。
今年もスタッフとして、堀江貴文さん主演のミュージカル『クリスマス・キャロル』に参加しました。今回は、東京公演が終わる2日間をお手伝いしました。
いちばん楽しみにしていたのは、前回からどこが変わったのかを確かめること。小さな改善の積み重ねを観察するのは、本当に学びが多いです。 今回は、看板や電光掲示板が新たに加わり、さらに専用の「スクルージ紙幣」まで発行されていました。紙幣や看板、電光掲示板のグラフィックはどれも細部まで作り込まれていて、デザインへのこだわりに圧倒されました。
なかでも印象的だったのは、販売所で扱われていたスクルージ紙幣の中央に、“ホリエモン”こと堀江貴文さんの肖像があしらわれていたこと。ユーモアたっぷりの仕掛けで、作品の世界観と堀江さんのイメージが楽しく掛け合わされており、思わず笑顔になりました。
スタッフとして働く環境も心地よく、昼と夜のお弁当まで用意されていてとても美味しかったです。細やかな配慮のおかげで、現場は終始働きやすい雰囲気でした。 あらためて、「良いプロジェクトは、スタッフへの配慮まで行き届いている」ことを実感しました。
レポート執筆者:床次 佳浩 / Yoshihiro Tokonami
編集:D-Lab AIチャンネル「D-Lab AI」
https://daigovideolab.jp/ai/landing
校閲:OpenAI「ChatGPT Pro」
https://openai.com/ja-JP/chatgpt/overview/
最新記事 by 床次 佳浩 / Yoshihiro Tokonami (全て見る)
- 『ベーシックインカム実験とAIが教えてくれた「価値のつくり方」』HIUベーシックインカムレポート【11月】 - 2025年11月30日
- 『約300作の中、準グランプリを取りました!』HIUベーシックインカムレポート【10月】 - 2025年10月31日
- 『速さより深さ――ChatGPT 5 Proが「調べる」を変えた日』HIUベーシックインカムレポート【9月】 - 2025年10月1日